
人生100年時代。
以前は早く死亡するリスクに備える必要があったといえます。
特に世帯主が死亡した後の家族の生活資金や子どもの教育資金に備える必要がありました。
現在はどうでしょう。
もちろん子どもがいる世帯では、子どもが自立するまでの世帯主の死亡保障は必要になると思います。
しかし、長生きのリスクが今は高いのです。
そこで、保険を活用してリスクに備える方法を考えてみたいと思います。
🔶保険の活用法
まず、保険というのは相互扶助の精神を基に成り立っています。
まず、保険というのは相互扶助の精神を基に成り立っています。
最近は保険会社も株式会社にしているところもありますが、株式会社にしているところも元は相互会社だったりします。
相互会社というのは、保険の契約者が構成員(社員)となって保険料を出し合い、誰かが亡くなったり、ケガや病気または事故にあった場合など万が一の時に、必要なお金(保険金)を支払うと言う仕組みです。
日本では保険業法により保険会社にのみ認められています。
以上のことから、保険というのは元々相互扶助によって成り立ち、少額の保険料で誰かに万が一のことが起こった時、契約者から集めた保険料で大きな額を支払うことができる仕組みとなっています。
ですので、本来保険は保険金が支払った金額以上に戻ってくる貯蓄型の保険にはあまり向いていません。
保険を活用する優先順位が高いのは以下の順となります。
① 子育て中の世帯主の死亡保障
② 現役世代の長期休業補償
③ 相続対策として終身保険の活用
※ただし健康保険へ加入している会社員は「傷病手当金」が出るので、それでも不足する分のみ保険を活用。
では、保険で年金など貯蓄することは難しいのでしょうか。
預金をしておいても、この低金利の時代にはお金はふえていかないですよね。
投資は元本割れリスクがあるのでしたくない思う人もいます。
保険の場合、保険料払い込み期間が短いと返戻率が高くなります。
私も、年金保険に加入していますが、30万円ずつ年払いで44歳より10年の保険料払い込み、60歳から10年間332,000円の受け取りで返戻率は110.67%となります。
これは返戻率が高いように見えます。
でも、これには高い手数料が入っています。そのため途中で解約すると保険料を支払った分は全額は戻ってこず、マイナスになります。 まず、保険というのは相互扶助の精神を基に成り立っています。 最近は保険会社も株式会社にしているところもありますが、相互会社のところもありますよね。
相互会社というのは、保険の契約者が構成員(社員)となって保険料を出し合い、誰かがなくなったり、ケガや病気または事故にあった場合など万が一の時に必要なお金(保険金)を支払うと言う仕組みです。
日本では保険業法により保険会社にのみ認められています。
以上のことから、保険というのは元々相互扶助によって成り立ち、少額の保険料で誰かに万が一のことが起こった時、契約者から集めた保険料で大きな額を支払うことができる仕組みとなっています。
ですので、本来保険は保険金が支払った金額以上に戻ってくる貯蓄型の保険にはあまり向いていません。
保険を活用する優先順位が高いのは以下の順となります。
① 子育て中の世帯主の死亡保障
② 現役世代の長期休業補償
③ 相続対策として終身保険の活用
※ただし健康保険へ加入している会社員は「傷病手当金」が出るので、それでも不足する分のみ保険を活用。
では、保険で年金など貯蓄することは難しいのでしょうか。
預金をしておいても、この低金利の時代にはお金はふえていかないですよね。
投資は元本割れリスクがあるのでしたくない思う人もいます。
保険の場合、保険料払い込み期間が短いと返戻率が高くなります。
私も、年金保険に加入していますが、30万円ずつ年払いで44歳より10年の保険料払い込みで60歳から10年間332,000円の受け取りで返戻率は、110.67%となります。
これは返戻率が高いように見えます。
でも、これには高い手数料が入っています。そのため途中で解約すると保険料を支払った分は全額は戻ってこず、マイナスになります。
🔶トンチン年金
ちょっと面白い保険商品で、トンチン年金というものがあります。
保険は相互扶助の精神が基になっていると述べましたが、ある意味この保険はその精神に則った保険といえます。
この保険は、簡単に言えば生き残った人が多く受け取れるというものです。 具体的な保険商品は、日本生命「グランエイジ」、第一生命「ながいき物語」 、太陽生命「100歳時代年金」などがあります。
これらの保険は多くの人が掛けた保険料を長く生きた人だけが多く受け取れるのです。
ですので、途中解約をすると解約返戻金は払込保険料の約7割しか戻ってっこず、年金受け取り前に死亡すると解約扱いになります。
加入年齢は50歳以上になります。
損益分岐年齢は各社1歳くらいの差はありますが、男性が90歳位、女性が95歳位となっています。
100歳時の返戻率は各社差がありますが、男性で150~170%、女性で120~130%となります。(2018年時点) まさに生き残った人だけが多く受け取れるのです❗
この3社のトンチン年金には「保証期間付終身保険」と「確定年金」がありますが、 長生きのリスクに備えるには、やはり終身保険だと私は思います。
ちなみに厚労省によると、2015年に65歳を迎えた1950年生まれでは、男性の35%、女性の60%が90歳まで長生きする見込みだといいます。
一方、1990年生まれでは、現在の高齢者世代よりも長生きする確率が高くなり、男性の44%、女性の69%が90歳まで生存するとしています。
また女性が100歳まで生きる確率は1980年生まれと1990年生まれがもっとも高く、ともに20%でした。
なお、日本の将来推計人口(2017年)によると、2065年の平均寿命は、男性84.95歳、女性91.35歳。現在(男性81.09歳、女性87.26歳)より約4年延伸すると推計されている。
現在、健康で長生きのリスクに備えたい場合にはこんな保険を活用するのもアリなのではないでしょうか。

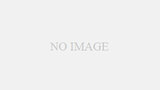
コメント